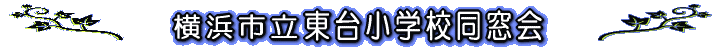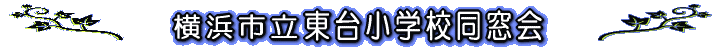| 明治27年~ 大正元年~ 昭和元年~ 平成元年~ |
 |
9代 坪田英俊
S5.12.24~S12.7.31 |
 |
10代 保谷二郎
S12.8.1~S24.4.14 |
 |
11代 平野健三
S24.4.15~S30.5.31 |
 |
12代 千葉勝夫
S30.6.1~S36.8.1 |
 |
13代 福島敏夫
S36.9.1~S42.9.1 |
 |
14代 石黒利公
S42,9,2~S45,8,31 |
 |
15代 佐藤一治
S45,9,1~S51,4,15 |
 |
16代 千葉富士雄
S51.4.16~S55.8.31 |
 |
17代 田井中分四郎
S55.9.1~ |
 |
18代 川村茂富
|
 |
19代 萩原正一
|
|
|
| 年号(西暦) |
沿 革 |
| 昭和 |
|
| 2 (1927) |
・学校の名前が横浜市鶴見尋常高等小学校に変わった。 |
| 3 (1928) |
・学校の場所が東台の丘の上に移った。
・鶴見区東寺尾町2052番地に、木造2階建ての14教室を建てて 移ってきた。(今の学校の場所) |
| 4 (1929) |
・学校の名前が横浜市東台尋常高等小学校に変わった。
・鶴見町立青年訓練所の名前が東台青年訓練所に変わった。 |
| 5 (1930) |
・生徒数862人、先生27人、坪田英俊校長(9代)。 |
| 6 (1931) |
・高等科を隣の学校に移して尋常科だけの小学校になった。
・イタリアの大地震に自治会が見舞状を出したので、イタリア領事が学校に来て、ムッソリーニ首相のお礼の言葉を
伝えた。
・東福寺の前の古い校舎を取り壊した。本館だけは分解して子安尋常高等小学校に運び後者に建てなおした。
・東台青年訓練所が実業補習学校になった。 |
| 7 (1932) |
・歯科医師小泉徳蔵先生が校医さんになった。
・イタリアの首相から震災の見舞状のお礼に、写真アルバムが送られてきた。 |
| 8 (1933) |
・皇太子殿下誕生の記念に校旗を作った。
・6年生の生徒自治会代表が、鳩山文部大臣に面接した。 |
| 9 (1934) |
・本校創立40周年記念式をした。 |
| 10(1935) |
・木造2階建て校舎(6教室)を増築した。
・東台実業補習学校が横浜市立東台青年学校に変わった。 |
| 12(1937) |
・生徒数1,228人、先生23人、保谷二郎校長(10代)。 |
| 14(1939) |
・学校の土地に約700㎡の市の土地を加えて広くした。
・木造2階校舎(9教室、今のC棟の所)と、木造の講堂(今の保健室の所)を増築した。 |
| 15(1940) |
・二宮尊徳の石造を建てた。(今のA棟の東の所)。台座の費用は全校生徒毎月1銭ずつの貯金、像は深堀辰三郎さんが寄付した。 |
| 16(1941) |
太平洋戦争始まる。
・学校の名前が東台国民学校に変わった。
・東台国民学校から岸谷国民学校が分かれて開校した。
・本校の生徒361人が岸谷国民学校に移った。 |
| 17(1942) |
・国民学校の生徒の最初のレントゲンさつえいを、鶴見保健所で始めた。 |
| 18(1943) |
・学校で食べ物を作り、生徒の栄養に食べさせた。
・東台青年学校横浜市立豊岡青年学校に合併した。 |
| 19(1944) |
・創立50周年記念日を迎えたが、お祝いはできなかった。
・第1次学どう集団疎開が出発した。(8月14日)
・生徒286人、先生たち20人と足柄上郡曽我村へ(今の小田原市)。宿泊した所は曽我小学校の校舎と、
4つのお寺の建物、このあと1年2か月ここで生活した。
・生徒がそかいしたあと、学校の教室を東芝電気会社に、講堂を食りょう倉庫に貸した。 |
20(1945)
8月 |
・第2次学どう集団そかいが出発した。(4月15日)
・生徒272人、先生10人、第1次の寮のほかに、曽我村の公会堂と2つのお寺に分かれて生活した。
・そかいしない残留組の生徒を、残りの女の先生たちが、近くの宝蔵院というお寺と会社の寮5カ所に分けて教
えた。
・生徒の栄養のため、学校でブタを飼っていた。
太平洋戦争終わる。
・10月26日、集団そかいの生徒たちが曽我村から帰ってきた。 |
| 22(1947) |
・学校の名前が、横浜市立東台小学校に変わった。
・東台小学校PTAがはじめてできた。双葉会といった。
・会員の数は2,950人であった。
・新しくできた寺尾中学校は、校舎がないので、東台小学校の中の6教室を使って開校した。 |
| 23(1948) |
・学校給食のため、給食調理場を作った。 |
| 24(1949) |
・生徒数2,255人、先生48人、平野健三校長(11代)。
・PTAのお金で学校の土地を広くした。 |
| 25(1950) |
・生徒の人数が増えて、教室が足りないので2部授業をした。
・県の競書大会で学校賞3位になった。
・PTAは2部授業をなくすため、新校建設促進会という会を作って、運動した。
・市有地を加えて校地を広くした。 |
| 26(1951) |
・教室が足りないので、東寺尾の鶴見学園の10教室を借りて、546人の生徒がそこで学習した。
・学校の土地のとなりの土地を借りて、給食調理場のしき地にした。 |
| 28(1953) |
・県の競書大会で学校賞2位になった。
・依田清さんが二宮金次郎の像を寄付してくれた。
・創立60周年のため、PTAが記念整備期成会をつくった。 |
| 29(1954) |
・県の競書大会で学校賞2位になった。
・内科医師真田哲雄先生が校医さんになった。
・創立60周年記念式をした。その記念に校歌をつくった。作詞薮田義雄先生、作曲下総晥一先生(光の子の歌)
・60周年記念に寄付してもらったもの。オルガン、けんび鏡、ジャングルジム、鉄棒、砂場、登り棒、
国旗けいよう塔、 優勝旗など。
・東台小学校の第2分校を、東寺尾町884番地につくった。 |
| 30(1955) |
・第2分校が横浜市立寺尾小学校となって独立した。
・生徒数2,011人、先生40人、千葉勝夫校長(12代)
・東台分校が寺尾小学校の分校となった。 |
| 31(1956) |
・木造2階校舎(4教室)を増築した。
・太平洋戦争の時の、アメリカ軍のかまぼこ型の建物を運動場に建てて、学校図書館にした。 |
| 33(1958) |
・学校の中に、学用品を売る店ができた。 |
| 35(1960) |
・東台小学校でははじめての鉄きん校舎、A棟の南6教室を建てた。
・そのため講堂と図書館の場所を移した。
・学校の隣の土地を買って、校庭を広くした。
・運動場の南がわをほそうした。 |
| 36(1961) |
・生徒数1,661人、先生44人、福島敏夫校長(13代)。
・保健室をつくった。 |
| 37(1962) |
・創立70周年の記念に水泳プールをつくった。更衣室とろか設備は、地元の人々が寄付した。 |
| 39(1964) |
・本校創立70周年記念式をした。 |
| 42(1967) |
・生徒数1,241人、先生37人、石黒利公校長(14代)。 |
| 43(1968) |
・眼科医師國谷喜美子先生が校医さんになった。 |
| 44(1969) |
・校舎A棟の北半分を鉄筋3階にする工事をした。
・工事のため運動場にプレハブ教室を6教室建てた。 |
| 45(1970) |
・校舎A棟が全部鉄筋3階になり、給食室も完成した。
・6月18日に落成記念祝賀式をした。
・生徒数1,251人、先生39人、佐藤一治校長(15代)。 |
| 47(1972) |
・校庭に池を作り、ろく木も建てた。
・暖房が石油ストーブになり、石油倉庫を建てた。
・白井充子さんが学校薬剤師になった。 |
| 48(1973) |
・校舎B棟の西半分も鉄筋になった。焼却炉を作った。 |
| 49(1974) |
・B棟東半分を鉄筋にする工事のため、運動場にプレハブの6教室を建てた。
・本校創立80周年記念式をした。 |
| 50(1975) |
・校舎A 、B棟を鉄筋にする工事が完成した。
・木造の講堂は自身にあぶないので取りこわした。
・寺尾小学校の体育館を借りて卒業式をした。 |
| 51(1976) |
・生徒数1,253人、先生42人、千葉富士雄校長(16代)。
・未完成の新体育館で卒業式をした。 |
| 52(1977) |
・校舎C棟とD棟を鉄筋コンクリートにする工事が、全部完成して木造校舎はなくなり、
体育館も完成した。
・5月28日、校舎鉄筋化完了祝賀会をした。
・校庭に木を植えたり、さくや門を作る工事も完成した。 |
| 53(1978) |
・町に下水道ができたので、構内の浄化槽をなくした。 |
| 55(1980) |
・生徒数1,329人、先生42人、田井中分四郎校長(17代) |
| 56(1981) |
・県の国際ビエンナーレ展で、大賞を受けたポーランド少年と韓国少女を迎えて、
国際交換会をした。
・プールの改修工事で、水洗便所、シャワー、ろか機室をつくった。 |
| 57(1982) |
・生徒がふえたので、A棟の図書室を変えて教室にした。
・学校の中の学用品の店をやめた。(24年間あった)
・障害のある子どもが、通学できるように工事をした。 |
| 58(19839 |
・便所の水を節約する節水装置をつけた。
・耳鼻科医師田仲博之先生が校医となった。 |
| 59(1984) |
・創立90周年記念式と記念の運動会をした。
校舎A棟1階と給食室を広くする工事をした。
・新しい学校図書館の建物(178㎡)が完成した。 |
| 60(1985) |
・休みの日や夜の間、学校の校舎を守る管理員の仕事をやめて、警備保障会社にまかせた。
・創立90周年記念誌を発行した。
・A棟一階と給食室、技術員室をきれいにする工事が行われ地域開放型の図書館も新しくできた。
・創立90周年記念誌「ひがしだい90年史」が完成した。 |
| 61(1986) |
・生徒数1,218人、先生43人、川村茂富校長(18代)
・帰国子女教育実践推進校に指定された。 |
| 62(1987) |
・プール塗装、国際理解教室で「世界の物産展」開催 |
| 63(1988) |
・生徒数1,108人、先生41人、萩原正一校長(19代)
・A棟の二階、三階をきれいにする工事が行われた。
・シエラレオ援助活動が始まった。 |